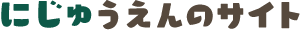発売:2020/5/1 レーベル:シャレードパール文庫

[公式サイトで見る] [Kindle] [パピレス] [honto] [Reader Store] [BOOK☆WALKER] [BookLive!] [楽天ブックス] [7net] [シーモア]
![]() 関連SS
関連SS![]()
シャレードパール文庫さんからの作品とは直接関係ないですが、同じキャラクターの出るSSを別の機会に書いていましたのでこちらにも掲載します。
[1]親友の距離………1,556文字(→ページ内リンク)
[2]足首と心臓の音…1,423文字(→ページ内リンク)
『親友の距離』
「たまには見てみたいな。玲一(れいいち)の酔ったとこ」
俺はテーブルの向かいにいる親友の顔を覗き込む。すると彼は手元のメニューから顔を上げ、怪訝そうな目で俺を見た。
金曜午後七時。都会の片隅にあるバルは、ステーキソースとワインの香り、それから落ち着いたミュージックに包まれている。
「俺が飲んだら誰が運転する」
向かいから、つれない返事が返ってきた。店の裏手にあるパーキングには、俺たちの足であるこいつの車が停めてある。
「じゃあ俺が運転する」
「なんで俺だけ飲むんだ」
「だったら一緒に飲もう。酔いが覚めてから帰る、それでよくないか?」
「面倒くさいやつだな……」
ぼやきながらも玲一は、料理のほかにワインを一本注文した。
「やった、グラスはふたつお願いします!」
俺はウェイターに念押しする。するとテーブルの向こうからはため息がひとつ。
「そんな嫌そうにしなくてもいいだろー」
「前にも話したが、俺は酒を飲むことにあまり前向きな価値を見いだせない」
そうなんだ。このお堅い親友は飲めないわけじゃないんだが、積極的には飲みたがらない。特に今は大学の講師をしていることもあって、外で飲んで酔ったところを人に見られるのは得策じゃないと考えているんだ。
分かる気もするけれど、そんなんじゃ肩が凝らないのかと思ってしまう。学生時代は、一緒にたくさん馬鹿なこともやったのに。
そういえばこいつの笑顔を、最近見ていない気がした。そこで俺はこの堅物を口説きにかかる。
「酒はコミュニケーションだ! それだけでも積極的な価値があるだろう」
「一人でも飲むくせに?」
「それはそれ! でも今はお前と飲みたいの! 飲んで本音を語り合う、みたいなの? たまにはいいじゃん」
「俺とお前に本音も建前もないだろう」
さも当たり前のように返される。
「だとしても、俺は、お前がわざわざ口にしない気持ちも聞きたいの」
運ばれてきた曇りのないグラスに、赤ワインを多めに注いで向かいの男に押しつけた。
それから三十分後――。
ボトルが空になっても、玲一はネクタイも緩めず平気そうな顔をしていた。
「なんでだよー……」
俺は自分のより、向かいのグラスにたくさん注いでいたのにどういうことなのか。せっせと飲ませて酔ってくれないんじゃつまらない。
「水もらおう」
玲一が気遣うような視線をこちらに向けた。
「もう一本いこうよ」
「ペース早いだろ」
「いやいや、俺ばっかり飲んでるみたいに言うなよ。ってかお前の摂取したアルコールはどこ行ったんだ」
「血中に。それから肝臓が徐々に分解してくれる」
「肝臓仕事しすぎだろー!」
思わず唾が飛んで、それから玲一がフッと笑った。
もう一度口へ運ぼうとしたグラスは空だった。口寂しい思いでいると……。
「てる、口開けっぱなし」
向かいから伸びてきた手に、顎を軽く押さえられた。あいていたのはボトルとグラスだけじゃなかったらしい。
俺に触れた手は下唇をかすめて離れていく。
(なんだ? この空気は……)
玲一がおもむろにテーブルに両肘を突き、こちらに顔を寄せた。
「……何?」
「いや……」
黒いまつげの奥の瞳が、間接照明の光を受けて色めく。
「俺がどうして外で飲みたがらないか、分かるよな? お前のそういう顔、あまり人に見せたくないからだ」
囁く声が、普段にはないやわらかな響きを帯びていた。顔色は変わらないけれど、こいつも酔っているんだなと理解する。
(あー……なんかこれ、面白い!)
気持ちが浮き足立つ。
「なあ玲一、ワイン注文しないなら、どっかほかで飲み直そう。俺、お前の隣に座りたい」
俺たちの間に四角いテーブルは要らない気がした。
「お前なあ。聞いてなかったのか? いま俺が言ったこと」
呆れ顔で言うけれど、なんだかんだでこいつは俺のワガママを聞いてくれる。俺はそれを知っていた。
午後七時半、週末の夜はこれからだ――。
<了>
『足首と心臓の音』
「なあてる。最近は酒も減ったと思ってたのに、ボーリングでねんざってなんなんだ」
ボーリング場の中まで迎えに来た親友は、立ち上がれずにいる俺を冷ややかに見下ろしていた。
こめかみに青筋が立っている。
「二八にもなって学生気分が抜けないのか」
二言三言と小言が続いた。
「怪我は仕方ないだろー! そんな怒ることないじゃないか」
迎えに来させて申し訳ないと思いつつも、向こうの態度が態度なだけに俺もムッとしてしまう。
「どうせ無駄にはしゃいでたんだろ」
「無駄にってなんだよ。たまにははしゃいだっていいだろ……」
「それで怪我していたら世話ないな」
彼の腕が伸びてきて、俺は思わず首をすくめる。
けれどもその腕は、俺を抱き上げるためのものだった。
「おいっ、玲一! ちょっと待て……」
二八にもなって、人前で男に抱き上げられる方が恥ずかしい。
けれども彼は問答無用で俺を肩に担ぎ上げた。
目線が上がり、夜のボーリング場の景色がよく見える。
近くを通りかかった人の驚いた顔、隣のレーンにいる女の子たちの熱い眼差し――彼女たちは玲一に見とれている――、それから苦笑いする俺の同僚たちの姿も目に映った。
「下ろせ!」
こんなの恥ずかしすぎる。
「いいから大人しくしてろ」
親友は聞く耳を持たなかった。
「なんでここまでするんだ!」
「歩くと余計に足を痛めるだろ」
「過保護か!」
いや、過保護なんだ、実際。
「こいつの荷物は……」
玲一に聞かれて、同僚が俺の荷物を彼に差し出す。
過保護な親友は俺を担いでいるのとは逆の手で、俺の靴とバッグを受け取った。
昔からこうだった。失敗するのは俺で、玲一は助けに来るヒーローだ。
逆の立場だった頃もあったけど、それは本当に小さい時だけで。中学に上がった頃には、すでに今の関係が確立していた。
玲一は完璧な男で、俺は馬鹿でドジな引き立て役だ。
ひがんでいるわけじゃない。けど助けられるばっかりじゃ、俺のちっぽけなプライドだって傷つく。
ところが俺を車まで担いでいった玲一は、俺を助手席に下ろすとひざの上に頭を乗せてきた。
「……なんだよ」
その行動に戸惑う。
「てる……」
「だからなんだよ」
「あまり嫉妬させるな」
人気のない地下駐車場で、わずかに揺れる瞳が俺を映した。
「え……この状況で、何にどう嫉妬するわけ?」
玲一の形のいい唇が、何か言おうとして止まる。
「…………」
「……………………」
見つめられ、こっちも言葉が出てこない。
片ひざを車のドアフレームの縁に置いていた彼が、ほんの少し伸び上がった。
顔が近づいてドキリとする。
けれど玲一はそのまま立ち上がり、運転席の方へ回っていってしまった。
(え……なに……)
俺の心臓はせわしなく鳴り続ける。
それから彼は、運転席でたばこに火を付けてから口を開いた。
「俺がすぐに来なかったら、てるは他のヤツに手を借りてただろ」
「まあ、そうだろうな」
足首の痛みが引かなければ、同僚の誰かに手を借りてタクシーに乗るしかなかった。
「それが?」
聞き返して数秒、俺はハッと息を呑む。
俺の質問から間があったせいで、玲一のセリフがその答えだと分からなかった。
「お前……、俺が他のヤツに手を借りるのが嫌なわけ?」
車が駐車場を滑り出す。
親友は答えの代わりにたばこの煙を吐き出した。
「気づけよ」
また少ししてからぼそっと言われる。横顔は来た時と同じ怒り顔のままだ。
それなのに、二人でいる空気が甘酸っぱく感じられて……。
足首がズキズキするのと同じくらい、胸の鼓動が騒いで落ち着かなかった――。
<了>